-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
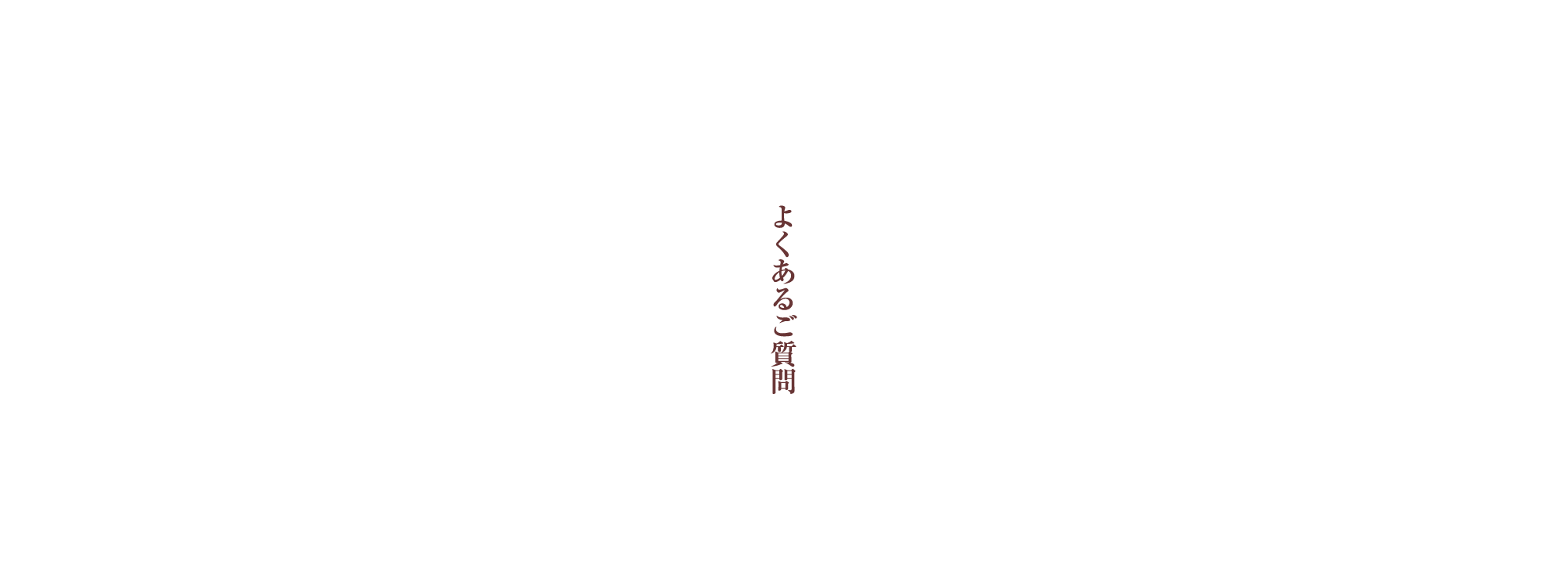
新年あけましておめでとうございます。旧年中は多くの方にご縁を頂き、心より御礼申し上げます。本年も「ご家族に寄り添う葬儀」を第一に、誠実な対応を心がけてまいります。寒さの厳しい季節となりますが、皆様どうぞご自愛ください。
1月の時候と暮らしの話題 1月は一年の始まりであり、心を新たにする月です。寒さが最も厳しく、体調を崩しやすい時期でもあります。特にご高齢の方は
・室内の温度差
・脱水症状
・感染症
に注意が必要です。日常の声かけや見守りが大切な季節です。
1月の仏事・行事
・元日~三が日:年神様をお迎えする期間
・1月7日:七草粥
・1月15日:小正月
・初命日・祥月命日を迎える方も多い時期です
年始は慌ただしく、法要の準備が後回しになりがちです。早めのご相談で、落ち着いたご供養が可能になります。
葬儀・法要についてのワンポイント
「事前に決めておくと安心なこと」
・連絡先(親族・菩提寺)
・希望される葬儀の形式
・ご予算の目安
事前相談は「縁起が悪い」ものではなく、ご家族の負担を減らす大切な備えです。無料でのご相談も承っております。
●冬至(とうじ)ーいのちを思う季節
一年でもっとも昼が短く、夜が永くなる「冬至」。古くから日本では、太陽の力が一番弱まる日とされ、ここを境に再び日の力が強まっていくことから「一陽来復(いちようらいふく)」=悪いことが続いた後に幸福が訪れる兆しとして大切にされてきました。
●ゆず湯に込められた願い
冬至と言えば「ゆず湯」。無病息災を願い、体を温め、一年の厄を祓うとされます。寒さが深まり体調を崩しやすい時期でもありますので、温かいお風呂でゆったりと心身を整えたいものです。
●かぼちゃ(南瓜)を食べる理由
保存がきき、栄養価も高いかぼちゃは、冬場の貴重な滋養。“運盛り(うんもり)”といって「ん」のつく食べ物を頂くことで運気が上向くと考えられてきました。
●冬至は「区切り」の日でもあります
一年の中で光がいちばん短い日が、翌日から少しずつ明るくなっていく。この自然の流れに、季節の移ろいは静かな支えとなることがあります。当社では、年末年始のご相談や仏事に関するお問い合わせも随時承っております。どうぞご無理のない範囲でお声がけください。
【12月の行事と風習】
冬至(12月22日)一年で最も昼が短い日。ゆず湯に入ることで「無病息災」を願う風習があります。
年末の大掃除 古くから「新年の歳神様を気持ちよくお迎えするため」に行われてきた行事です。無理のない範囲で、少しずつ進めて行くのがおすすめです。
除夜の鐘 煩悩の数と言われる108階の鐘を聞きながら、新しい一年が清らかに始まるよう願います。
【葬儀・終活ワンポイント】年末は家族や親族が集まりやすい時期。エンディングノートの確認や、ご希望の葬儀形式について話し合う良いきっかけになります。
・ご自宅でできるチェック
・遺影の準備
・保険や連絡先の整理
・お墓や納骨についての確認
当社では「終活の無料相談」を随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
【おしらせ】
・24時間365日いつでもご相談可能
・事前相談でお見積り・会館見学 無料
・相続・遺品整理についてのご紹介もできます
【最後に】
一年間、皆様からの温かいご支援に心より感謝申し上げます。
どうぞ良いお年をお迎えください。
来年も変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。
11月に入り、朝夕の冷え込みが厳しくなってまいりました。日中との寒暖差が大きい時期でもあり、体調を崩される方が増える季節です。皆様におかれましては、どうぞご自愛の上お過ごしください。
今月は、文化の日や七五三など、家族で過ごす行事が多く、地域の神社仏閣にも参拝者が増える時期です。また11月9日から15日は「秋の火災予防運動」が実施され、暖房器具の使用開始に伴う家裁への注意喚起が全国で進められます。これから乾燥が進みますので、住宅用の火災警報器の点検や暖房器具の整備をおすすめいたします。
私ども葬儀社では、日頃より地域の皆様が安心して生活いただけるよう、葬儀に関するご相談を随時受け付けております。
「もしもの時の流れを知っておきたい」
「費用を事前に確認したい」
「家族に負担がかからない準備をしておきたい」
といった内容も含め、どのようなご質問でもお気軽にお問い合わせください。
また、近年は単身世帯の増加やご家族の高齢化に伴い、事前相談や生前整理に関するご相談が増えております。当社では、葬儀後の各種手続き、遺品整理、納骨や法要に関するお手伝いも可能です。必要に応じて、信頼できる専門業者や士業へのご紹介も行っております。
11月は一年の締めくくりに向けた準備を始める時期でもあります。ご家族との時間を大切にしつつ、安心して冬を迎えられるよう、お役に立てる情報を今後も発信してまいります。
本格的な寒さに向かう折、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。