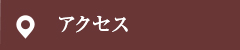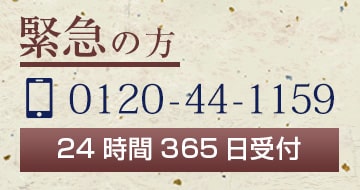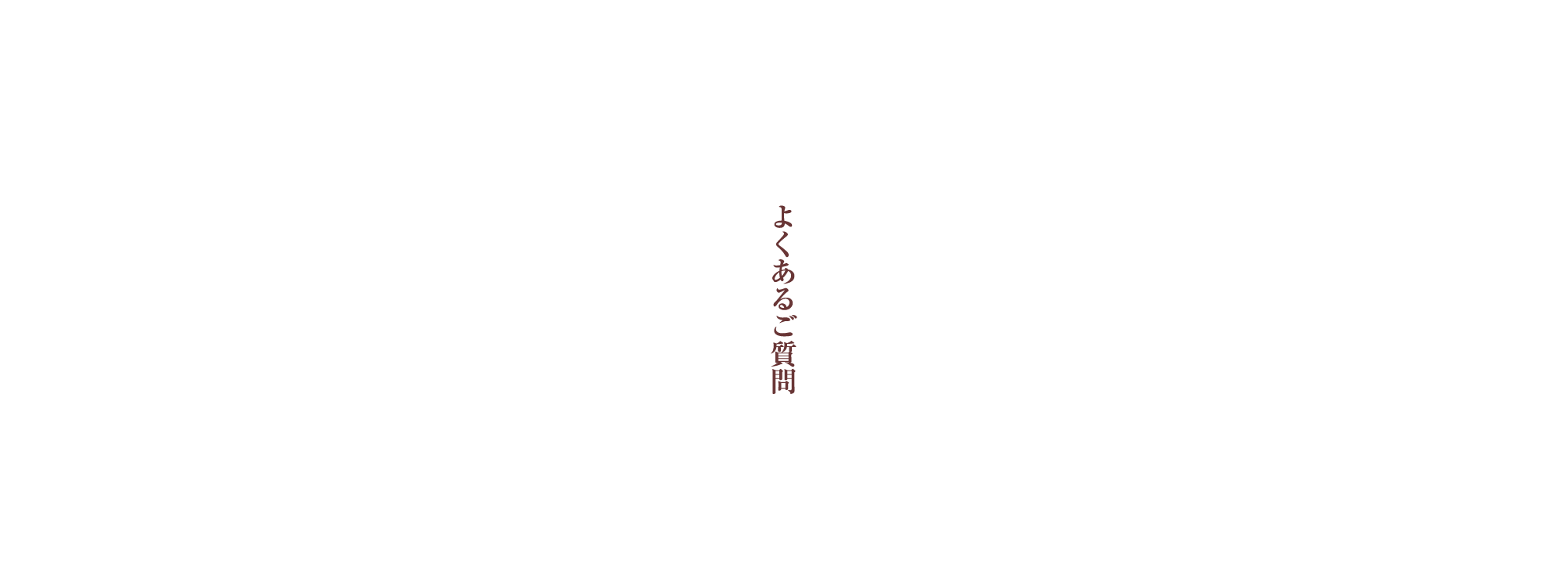
月別アーカイブ: 2025年2月
節分
節分(せつぶん)日本の伝統的な行事で、立春の前日に行われます。この日は「季節を分ける」という意味があり、冬から春への移り変わりを示します。節分には、悪霊を追い払い、服を招くための様々な風習があります。
豆まき:鬼(おに)役の人に向かって「鬼は外、福は内」と言いながら豆をまきます。これは邪気を払うと同時に福を呼び込むためです。まいた豆は都市の数だけ食べると良いとされています。
鬼打ち:鬼の面をかぶった人を追い払う儀式です。子供たちが特に楽しみにする行事の一つです。
恵方巻き(えほうまき):節分に、特定の方角を向いて無言で巻きずしを食べる習慣です。
節分は、単に季節の変わり目を祝うだけでなく、家族や地域の人々とのきずなを深める機会でもあります。多くの神社お寺でも、節分の行事が行われ、豆まきや厄除けの祈願が行われます。